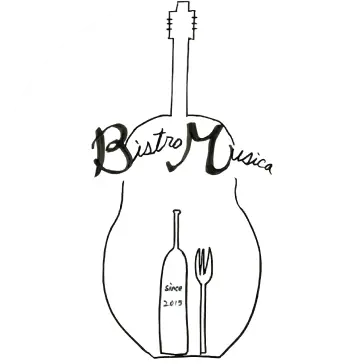『くたばれペアリング!?』〜ペアリングの功罪〜イベントを終えて
10月5日にお世話になっているワイン屋さんと一緒にイベントをやりました。
=秋の食材と日本ワインの会=
料理5品と山梨のフジクレールワイナリーのワイン5本のペアリングを楽しむ会。
なんと途中でフジクレールの澤村社長がお忙しい中ご来店いただき、
お話しをしていただくと言うサプライズ。
たまたま東京にいらしゃったとのことでしたが、こんなことが起きるのもイベントならではですね。
こんな事もあり、参加していただいた方には楽しんでいただけたようでほっとしています。
イベントは色々準備が大変ですが、学ぶことも多く自分の成長につながりますね。
さて、そんなイベントでしたが、料理とワインの関係や楽しみ方について、
こんな事を改めて考えるキッカケにもなりました。
「ワインと料理のペアリング」──
それはいつの間にか、ワインを“正しく”楽しむためのルールのように語られるようになった気がする。
でも本当に必要なのか?
ペアリングって、もっと自由で、もっと人間的でいいんじゃないかと。
=ワインって難しそう=
たまに「ワインの事」わからないんです。
お客さんからこんな声をいただくことがあります。
この「わからない」にはどんな味なのか?
そして「料理に合わせたらいいのか?」と言う気持ちが含まれているのだと思います。
正直私もまだまだ「わからない」事だらけ。
でも「わからない」って、本当に悪いことなんでしょうか?
= ペアリングは正解じゃない。=
──美味しいよりも、楽しいを味わう。
「ワインと料理のペアリング」
それは、いつの間にか”ワインの楽しみ方の正解”のように語られるようになっている気がします。
でも、そもそもワインを楽しむって、そんなに難しい話なんでしょうか?
=美味しいと楽しいのちがい=
この事を考えるにあたり
「美味しい」と「楽しい」と言う2軸で見てみたいと思います。
私は食べる人には、美味しいと楽しいを感じてほしいと思っています。
で、この2つは似ているようでいて、まったく違う。
“美味しい”は感覚の喜び。
“楽しい”は体験の喜び。
そして、食事というのはこの2つが交わる場所にあるわけです。
いつも思っているし、お伝えしているのですが
「美味しい」は「楽しい」の中の一つの要素だと思っています。
知識や情報は”食”を楽しくするけれど、それだけでは美味しくはならない。
(美味しくする一つの要素ではあるかもしれませんが)
すっごい不愉快な気分やくら~い空気の中では
「美味しい」はその威力を発揮しずらい。
「美味しい」が暗い気持ちを明るい気持ちに切り替えるキッカケになることもありますけどね。
で、ペアリングの話。
=ペアリングは「楽しみ方のひとつ」=
ペアリングは「正解」ではなく、「遊び方のひとつ」だと思っています。
味の調和や香りの共鳴を探すのは確かに楽しい。
けれど、それは食の入口であって、出口ではありません。
ペアリングの本質は、”美味しい”よりも”楽しい”の比重が大きい。だからこそ重視するのはアリ。
でも、絶対じゃない。
目玉焼きに
・醤油?
・ソース?
・ケチャップ?
・塩?
・味噌?
・マヨネーズ?
それとも・・・
みたいなイメージでいいんじゃないかと。
こう考えるとかなりハードル下がりません?
= 家の外でも、“ペアリングよりも人”=
妻と食事に行ったとき、ワインを選ぶのは私の役目。
まず「赤の気分? 白の気分?」と聞いて、
そのあとでソムリエさんに何があるかを聞く。
そして妻の好みに合わせて選びます。
「この料理にはこっちの方が合いそうだけど、こっちの方が好みだと思う」
そんな風に、ちゃんと理由を添えて。
で、決めてもらう。
このときに“料理に合う”よりも、
“その人に合う”方を選ぶことのほうが多い。
だって、その方がきっと、楽しいですからね。
=「Don’t think. Feel」 =
ビールを買うときだって、「どんな料理に合うか」を考える人は少ないと思います。
ビールだって色々な味わいがありますが
「私はいつもスーパーDRY!!!」
みたいに好きな銘柄買いませんか?
ワインも同じ感覚でいいと思うんです。
「わからない」と感じることは恥ずかしいことじゃない。
むしろ、感覚を開くチャンスです。
“合う・合わない”ではなく、
“好き・気になる”でいい。
ワインももっと気楽で、もっと自由で、
そしてもっと人間的なものであって欲しいなと思います。
=誰が「いい」を決めたのか=
ワインとかって当たり年って言われる年がありますよね。
〇〇年のは美味しいみたいな。
でもその年のワインを飲んで美味しいか美味しくないかを決めるのは飲み手自身。
批評はあくまでいいとされている基準にどこまで近いか?だけ。
でも、その「いい」は誰が決めたのか?
ですよね。
もっと自信を持って美味しい・美味しくないを言っていいじゃないでしょうか?
美味しい美味しくないというか、好みかどうか?ですね。
美味しくないって言われると作り手はショックですし。。。
それに美味しい美味しくないっていうとなんか憚られることってありますよね。
こいつわかってないな~みたいに思われたらやだな~みたいな。
なので好き嫌いで判断して伝える自由が大事なんだな。
この基準ならペアリングも正解・不正解なんてなくなるし、もっと楽しめそう。
自分の「好きな味わい」を把握して、なんで好きなのか?苦手なのか?を知っておけば、
そんなに難しい事を考えずに料理もワインももっと楽しめる気がします。
この自分の好みを伝えられる自由を保ったお店でありたいですね。
= Bistroむじかのフィロソフィ=
料理もワインは”語る”ものではなく、”囲む”もの。そして”分け合う”もの。
料理もワインも主役ではなく、”美味しい時間”の脇役として寄り添う。
その日の空気、季節、会話の流れ、一緒に笑う人の表情──
それらすべてが、食体験としてその時間を特別にしてくれます。
さて、
こんな事を書いてきましたが別に「ペアリングなんて!」
「ワインなんて!」と思っているわけではありません。
楽しいし好きですよ。
むしろ反対で「ワイン」や「食」(特にフレンチ)が難しいものかのように思われている気がしているので、「そんな事ないんじゃない?」と伝えたいだけ。
そのハードルを上げる原因の一つに「料理とワインのペアリング」があるんじゃない?と。
あとは「カタカタ」なんだろうな。
なんてね。
= 自然派ワインと自由=
そんな私が自然派ワインを好きな理由は、そこにあります。
肩書きや権威よりも、自由であること。
tatooをして、ジーンズとTシャツで。
顎髭があって、そんな格好が似合うワイン。
決まりごとに縛られず、ラベルより中身で語り、
誰かの評価じゃなく、自分の感覚で選べる。
美味しさに肩書きはいらない。
あるのはただ、人間の感性と、ぶどうの姿。
なんか自由でいいかなって。
こうありたいですよね。
=最後に=
さっきも書きましたがペアリングを否定したいわけじゃありません。
むしろ、その中にたくさんの発見や笑顔がある。
ただ、それが絶対のルールじゃないというだけのこと。
知識は食を楽しくするけれど、美味しくするのはいつだって感性。
食に正解・不正解はありません。
あるとすればそれは「食中毒」だけですからね。
そんな楽しみ方があっても、いいんじゃないかなと思った。
一緒にもっと「食」の世界を楽しみましょ!
========
Bistroむじかとは
========
食を通して、感性と知性を満たす場所。
味わうことは、考えること。
考えることは、生きることを楽しむこと。
そんな場所でありたいと思っています。
お読みいただきありがとうございました。